
2008/5/15
art drops インタビュー 2008 vol.2 テーマ:「現実と虚構の狭間」 ドイケイコ
松江哲明さん/ドキュメンタリー監督 ―前編―

現実を演出した世界をつくる
一般的に“ドキュメンタリー”と聞くと、疑いもせず“すべて現実”と受け入れがちだ。しかし、ドキュメンタリー監督の松江哲明さんは「『嘘』のないドキュメンタリーはない」と言う。「例えばカメラ一台だけで現場に入るなら、その視点でしか状況を伝えられないから」。確かに、その映像は“すべて事実”とは言い難い。しかし、フィクションでもない。それこそ、現実と虚構のスレスレの狭間なのではないだろうか。そんな世界をつくりだす松江さんに迫ってみた。
■ とにかく映画が好きだった
1977年、東京都立川市で松江哲明さんは在日コリアンの父親と日本人の母親の間に生まれる。後に妹が生まれ、祖父母合わせ6人家族の長男として育つ。
「小さい時はウルトラマンとか特撮ものが好きで、よく父母にヒーローショーへ連れて行ってもらいました。ウルトラマンが変身する時の声が『あっぱーぽん!』って聞こえていたらしく、しょっちゅう言ってたみたいです(笑)」。
松江さんが6歳の時、映画好きの父親に連れられ初めて映画館を訪れる。
「『スター・ウォーズ ジェダイの復讐』でした。シリーズものの途中なので内容はよくわかんなかったけど、いろんな人が集まってひとつのスクリーンで観る、というのがアトラクションみたいで面白くって好きでした。それから映画にはまりましたね」。
その後、家族では『寅さん』と『東映まんがまつり(ただし実写のヒーローもの)』を、父親とふたりでは“大人の映画”を観に行くようになった。
「父親と行く映画の方が好きでした。自分の好きなものを観ることができたので」。
好きに映画を選ばせてくれる父親のおかげで、小学生ながらチャップリンの作品やアメリカン・ニューシネマ、大人びた洋画など幅広いジャンルの映画を観ることができた。また、“特撮もの好き”の延長でホラーやSF映画にも興味を持ち、仕掛けを調べて楽しんでいたと言う。
学校でも豊富な映画の話題からさまざまなタイプの友人と会話を楽しんでいた。

■ 人生最悪の時代
中学生の頃から週末は自分で計画を立てて映画を観に行くようになる。
「幼い頃からそろばんを習っていて、中学生の頃には1週間で2万円くらい稼いでいたんです。その資金をもとに、週末になると自分で“三本立て”をして、ひとりで電車に乗って、新宿とかの映画館へ足を運んでいました。毎回、映画を観た後はパンフレットを買って立ち食いそばを食べる。すごく楽しかったな」。
松江さんを相当の映画好き少年にしてしまった映画の魅力とは、一体何だったのだろう。
「逃げ場かな」。
意外な答えだった。
「中学生時代、モテたいと思ってバスケ部に入っていたんです。そこで人に合わせることを意識したんですが、地獄でした」。
元来スポーツが得意でなかったこと、皆に合わせるのが苦手な性格だったことから、二重の苦しみを味わう。
バスケの試合に参加した時は「負けろ負けろ」と思っていた。試合が早く終わったら、映画を観に行くことができるからだ。
そして、高校時代は『人生最悪の時代』だったと言う。
「授業中は本を読んでいました。休み中も本を読むか、もしくはトイレや水飲み場に行くか。とにかく周りからどう見られているかを凄く意識してたんです。
学校って皆を平均値にするところがあるじゃないですか。それが嫌でした。合わせることはもっと嫌でしたね」。
そんな時も、唯一自分を開放することができたのが映画だった。
「映画を観るとエラくなった気がするんです。同級生がバスケに勝った負けたと言ってることが小さく感じたり、異性を好きだ嫌いだと言うことも、自分は大人の恋愛を知っているし、とか。とにかく『俺の方が中身は大人だ』と周りを低く見ていましたね。
けど、現実においては全くの奥手で『違う人生を送りたい』『学校をさぼりたい』と思っていても全然できませんでしたが(笑)」。
映画は「逃げ場」となり、松江さんのアイデンティティーを確立させた。
当時、映画の他に、音楽や書籍なども同様に青春時代を支えた。中でも、大槻ケンヂさんの書籍『グミ・チョコレート・パイン』はバイブルだと言う。
「あの本があったから人生やって来れた気もしますよ」。
 |
 |
 |
|---|
大槻ケンヂ /著 『グミ・チョコレート・パイン』(左から)グミ編、チョコ編、パイン編
主人公の冴えない高校生、大橋賢三のあふれる性欲と、とめどないコンプレックス、そして純愛のあいだで揺れる“愛と青春の旅立ち”を綴った物語。大槻ケンヂ氏の自伝的大河小説と言われている。
■ ドキュメンタリー制作への道
そんな時代を乗り越えて辿りついた場所が日本映画学校だった。
「映画学校では“人に合わせなくてもいい”というのが凄く嬉しかった。自分の好きなものを表現して良くて、“そのまま”が認められるんです」。
また、当時、好きだった監督の中に北野武さんがいる。
「北野監督の映画は、派手なことをしなくても日常的なアクションですごいと思わせるんです。暴力描写とか好きでした。あと、なんか、これなら自分でも撮れるかも、って思っちゃったんです(笑)」。
北野作品は映画制作への後押しにもなった。しかし、実際、劇画を作成してみて「自分には劇画をつくる才能は無い」と感じる。
その後、卒業制作として自身の家族を描いたドキュメンタリー映画『あんにょんキムチ』(1999年)を撮影。この作品は、韓日青少年映画祭監督賞、山形国際ドキュメンタリー映画祭アジア千波万波特別賞などを受賞することになった。
 |
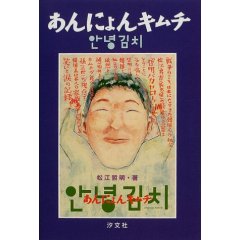 |
|---|
『あんにょんキムチ』監督:松江哲明、制作:山谷哲夫 (右上図は書籍『あんにょんキムチ』)
戦時中、日本へ渡った韓国人の祖父・松江勇吉(劉忠植)の最後の言葉は「哲明バカヤロー!」だった。そのことに気を病んだ松江さんは韓国と祖父のことを調べ始める。友人たちに自分が韓国人であることを告白したり、大嫌いなキムチを食べようと必死になったり……。
祖父を中心に、韓国系日本人の家族が歩んできた歴史や現在を、孫(三世)の視点でたどる笑いと涙の記録。
※このページに掲載されている記事・画像などの一切の無断使用は堅く禁じます。